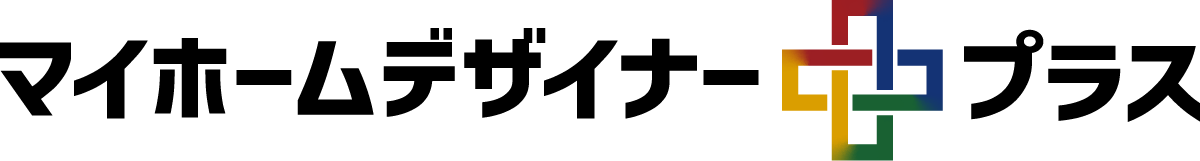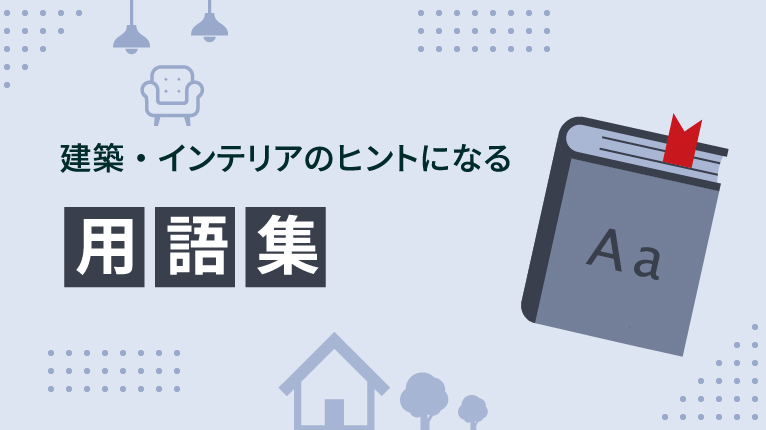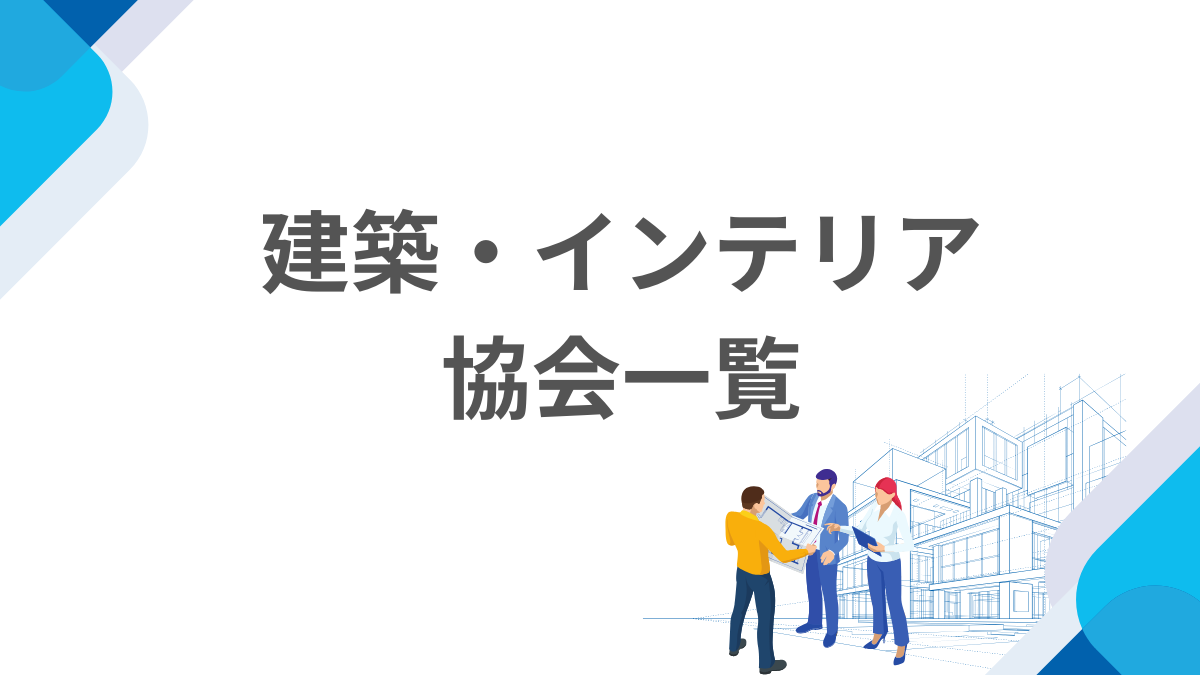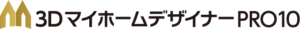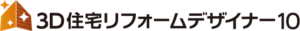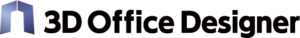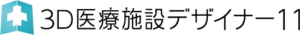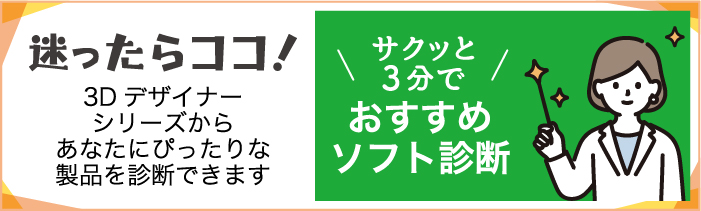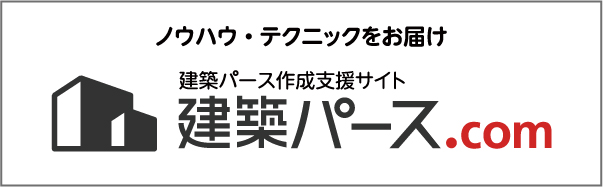防犯と防災から考える外構計画【後編】
- お役立ち

次に、防災の話をしましょう。
犯罪と同じく、常に私たちの生活と隣り合わせにある身の危険、それが災害です。
地震、台風、大雨、水害、雷、土砂災害、大雪、酷暑。
災害大国と呼ばれる日本ですが、この数年間だけでもほぼ全ての災害が記憶に残っているのではないでしょうか。
こちらも「防犯」と同様に「防災」という観点で、外構を考えていく必要があります。
「家」「自身」「家族」を守るために、その中でも「家の外まわり」=「外構」と関係性の深いものについて考えていきたいと思います。
外構から考える「防災対策」
地震
頻繁におこる大きな地震ですが、外構で防ぐ被害と外構が及ぼす被害、双方について考えねばなりません。
一番大きな問題は、現在社会問題にもなっている「塀」です。

塀を構築する素材や構造には様々な種類がありますが、とくに問題となっているのは、「補強コンクリートブロック造の塀」、もしくは「組積造の塀」です。
大きな地震の後のニュースで「塀が倒れた」と報じられる場合、ほとんどがこのどちらかです。
もともと鉄筋の入らない構造のもの、あるいは入るはずなのに適切に施工されていないもの、さらには耐用年数を著しく超えたものが倒壊していることがほとんどです。
適切に計画されて、正しく施工された「塀」は、地震で倒壊した家から人を守ってくれることもありますし、緊急車両の経路を塞がないよう瓦礫をせき止めてくれることもあります。
つまり、二次災害を起こさないために、適切な計画と施工が欠かせないのです。
古くからある「塀」で、もし何か事故が起きれば所有者・管理者の責任です。
耐用年数や建築時の法規制状況も含めて、現在の規格に適合しているかどうかを確認し、不適切であれば安全な状態に改善する必要があります。自治体によっては、条件を満たせば改善工事に補助金が出る場合もあります。悲しい事故を起こさないように、宅地内に古い塀がある方は積極的に確認と改善を行うようにしましょう。
なお、ブロック塀ついて、詳しくは別の機会で取り上げたいと思います。
台風(突風)

外構に関する防災で、地震の次に無視できないのが「台風」や、それに匹敵する「突風」です。
外構には、カーポート屋根や物置、目隠しフェンスなど、風圧に影響をうける構造物が非常に多くあります。これらの構造物を支えているのが、柱まわりをコンクリート等でしっかりと固め荷重をかけた「基礎」です。
カーポートやテラス屋根、フェンスなどを扱う主要なエクステリア金物メーカーでは、設置地域や、設置場所の地質や風速、設置したいサイズによって、適合商品や基礎の寸法が定められています。これらの基準を守り、適切な商品を選んで安全な設置をすることがなにより重要です。
また、風を面で受けるもの以外にも、稼働するゲートなど風に流されてしまいやすいものもあり、可動物や飛散物が原因で対物・対人の被害を出さないように注意が必要です。
各社ホームページでは、台風など自然災害時の商品の取り扱いについて、ユーザーに事前喚起していますので、それらを参考に日頃より対応をシミュレーションされておくことをお勧めします。
参考:自然災害への対応について(三協アルミ)
https://alumi.st-grp.co.jp/inquiry/disaster/wind_e.html
大雨・浸水

近年、「五月雨」や「夕立」「青時雨」といった季節の風物詩的な雨の様子は姿をひそめ、「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」などの災害級の大雨に関する言葉が増えたように思います。
河川氾濫や住宅浸水がニュースにならない年はないのでは、と思うほど頻繁に、大雨水害が発生していると感じます。
基本的な外構計画で考えておくべきことは、タイルなどの舗装材の選定等、滑りにくい床にする工夫や、宅内に降り注いだ雨水の処理方法です。
災害級の雨量となれば、川の氾濫(外水氾濫)は即避難となるでしょう。
一方で、排水処理能力の低下による氾濫(内水氾濫)が過去に起きた、あるいは繰り返されている土地では、可能であれば建築時に設計GLを道路より高めに設定する工夫も検討したいところです。
さらに、外周にブロック塀を効果的に配置し、緊急時には限られた開口部だけを臨時でせき止められるようにしておけば、被害を抑えられるでしょう。
そのような場面で役立つのが、折りたたみ収納できて再利用可能な軽量素材の組立て式止水板や、土を掘る必要がなく水だけで膨らむ土嚢袋です。
アクアブロック(日水化学工業株式会社)
https://aquablock.jp/
水に漬けるだけで、わずか3分で膨らむ吸水土のう。
省スペースで保管でき、非常時には20㎏相当の土のうとして浸水対策に力を発揮します。
画像提供:日水化学工業株式会社
最近では、一般家庭でも購入できる工夫に富んだ災害対策用品が増えています。こうしたものを想定に入れ、効果的に活用できる全体計画ができているとベストですね。
避難か、在宅避難か
災害の規模によっては、避難が必要になる場合もあります。
2025年7月にカムチャツカ半島付近で発生した大きな地震により、日本の広範囲に津波警報・注意報が出されました。結果的に、国内で大きな被害はなく解除に至りましたが、全国の多くの自治体で避難指示が出され、困惑した方も多かったのではないでしょうか?
そんな時、備えがあればすぐに行動に移せますが、何も準備ができていないと立ちすくんでしまいます。
特に今回は、かく言う私も「揺れも感じてないのに津波だなんて、、、」と困惑が先に立ち、すぐ行動できませんでした。日常からの備えが本当に大切なんだな、と深く反省しましたが、同じように感じた方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
ありがちなのは、玄関に非常用品を置いたものの、どどんと場所をとり、日常の暮らしが不便になってしまい、結局すぐに出せないような場所に片付けてしまった――そんな本末転倒を避けるためにも、家の外まわりを含めた非常用品の収納を考えてみてはいかがでしょうか。
最近は、玄関先に置けるようなおしゃれな物置や、草花で綺麗に彩られたプランター一体型のベンチ収納など、普段のおだやかな風景に溶け込むデザインで、異質感を持たせずに非常時の備えができる商品もあります。そんな日常の風景を保ちながら、非常時に役立つ備えを外構計画に取り入れていきませんか。

MODO/モド(株式会社ユニソン)
https://www.unison-net.com/gardenexterior/product/p82766/
普段はベンチやプランターとして暮らしに溶け込み、非常時には備蓄品をすぐ取り出せる防災ストッカーに。災害への備えと、日常の快適さを兼ね備えた外構アイテムです。
画像提供:株式会社ユニソン
また、「避難」とは、自治体に指定された避難所に身を寄せることに限りません。家族にご高齢の方やペットがいるなど、何らかの理由で避難所に移動できない場合は、災害発生後に家屋の安全が確認できれば「在宅避難」という方法をとることも一つの手段です。
たとえば、倒れた家財道具で室内にすぐには戻れない、あるいは室内が水浸しになってしまった場合でも、庭にウッドデッキやテラスなどの小上がりの床面があったなら。そこは一時避難場所になるでしょう。

そこにテントやテーブルセット、BBQ用品などのキャンプ道具があれば、ガスが止まっていても煮炊き・休息が可能です。アウトドアスキルは、災害時に大いに役に立ちます。
食料や日用品は、災害時に必要な量は維持しつつ、日常生活の中で消費しながら補充し在庫を回転させていく「ローリングストック」という意識を常日頃より持っていれば、無理なく確保できます。庭の家庭菜園も、自給自足までは難しくても、日々の糧や楽しみになりながら非常時に役に立つこともあるでしょう。
家の中だけでなく、外構計画にも日常のものを災害時に転用できる工夫をしておくことで、いざという時により安心です。
酷暑と緑化
最後に、もはや災害級と言っても過言ではない夏の「酷暑」と「家の外まわり」についてです。
地球温暖化が叫ばれて久しい昨今、これまでお伝えしてきた気象に関する事象・災害というのは、全て地球温暖化の進行が要因とされています。
温暖化を食い止めるために、これまで様々な対策が取られています。住宅においては、今年春に建築物省エネ法が改正され、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。
こうした住宅本体の省エネ化が「気温を上昇させる原因を抑えていく=緩和策」であるのに対し、「気温の上昇に耐えられるようにしていく=適応策」として非常に効果的なのが「緑化」と言われています。

じつは私は、外構の設計業務だけでなく、ウッドデッキ造作などの木工をしたり、植物を植えたり、育った庭をメンテナンスしたり、実際の現場に赴いて作業する仕事もしています。
年々と夏場の作業がキツくなり、空調服なしでは到底屋外作業などできないようになり、生命の危険を感じるほど。暑さ対策にかかる費用は、冬場のそれを軽く越したように思います。それくらいの変化が起きています。
今年の夏もあちこちの住宅街に足を運びましたが、一貫して言えるのは「緑が豊かな住宅街は涼しい」ということです。
植物はその本体に多くの水を含み、地中の根から水を吸い上げ、それを水蒸気として地上に放出する「蒸散」の作用によって表面温度を下げています。
これにより、周辺の気温も下がり、さらに本体がつくる「木陰」が周辺の日射を遮ることで、さらに涼しさを感じるのです。
昼間の日照で熱されたコンクリートやアスファルトは蓄熱してなかなか冷めませんが、植物に覆われた緑地は蓄熱が少なく、放射冷却によって表面温度も下がるため、夜間の温度差が発生します。

こうした植物が起こす効果が、まず1本の木から始まり、ひとかたまりの植え込み、家1軒のお庭、向こう三軒両隣、そして一画の住宅街、と帯・塊になっていくことで、その街全体の環境が良好になっていきます。
これは公共事業でもなく民間企業でもない、1軒1軒の個人の家の良識と努力、そして費用によって成立するものです。もはや他人事ではなくなった災害級の「酷暑」対策として、まずは自身や家族を含め、その土地に住む人々を守るために、緑ある街の維持と構築を継続していくことが今後ますます必要とされるのではないかと思います。
残念ながら、「手入れが大変」「虫が嫌い」「植物についてよく知らない」などの理由で、新築住宅のまわりに1本も植物を植えないケースや、中古住宅の購入際に、既存の豊かな木々をすべて伐採してしまうケースが少なからずあります。
私たち専門家は、見た目だけでない緑化の重要性について、もっとお客様に理解していただき、地域規模の快適な住環境を築けるよう努めていかねばならないと感じています。
安心と安全 まとめ
ここまで「防犯と防災」=「安心と安全」についてお話ししてきました。
防犯・防災に関して、さまざまなメーカーが多様な対策商品を開発し、目覚ましい進化を遂げています。また、様々なライフハックも発信されています。
そうした情報を上手にキャッチして、外構計画の際には専門家に相談しながら、デザイン性と防犯・防災どちらにも偏りのないようバランスよく、「いざという時だけの備え」ではなく「日常に組み込まれた無理のない備え」を自然に行えればそれがベストです。
ぜひ、日常を楽しく穏やかに過ごすために、緊急時への備えにも目を向けましょう。
そして「家の外まわり」=「外構」を上手に工夫し、「家」「自身」「家族」を守ってください!
[前編をみる] [後編]
筆者紹介
連載『家づくりは“外まわり”で決まる ― 外構から考える住まいづくり』
外構の大切さを理解し、心から安心できる住まいを築いてほしい——そんな思いから始まった「日本庭女子会〜にわとわに〜」のコラム。新築計画に役立つ外構の知識やアイデアを、月1回更新でお届けします。
プロフィール
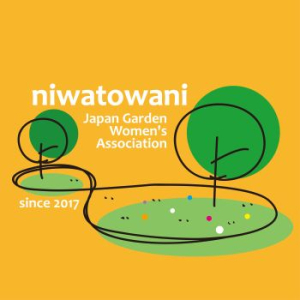
日本庭女子会〜にわとわに〜
エクステリア・ガーデン業界やそれをとりまく業種に従事する・携わる女性たちが、交流や情報交換を目的とし2017年に活動開始。
「庭や外部空間を美しく快適にすることが、住まいや暮らしを豊かに送るのに不可欠なことであり、ひいては日本の街並や景観・環境を美しく創り保ってゆくのに重要な役割を担っている」
また「住まい手だけでなく造り手・働き手の身になって考え、幅広い知識で美しく機能的な空間を造っているプロフェッショナルな女性たちがいることを知ってほしい」
そんな熱き想いを持った庭女子たちが、所属や経験・年齢を超え様々な切り口の委員会を組織し、日本各地で活動・躍動中。現在メンバー150人超。
https://niwatowani.jp/執筆者

芦川 美香 (あしかわ みか)
横浜市を拠点とするこの道25年超のエクステリア・ガーデンデザイナー。
株式会社アフロとモヒカン代表取締役。
「はじめのいっぽからさいごのちゃくちまで」を社のモットーに、日々お客様宅の外まわりをお客様らしく、美しく暮らしやすく整えるべく、設計・営業・現場に奔走中。
にわとわにプロフェッショナル会員、「美未備っと安心安全委員会」委員長、1級エクステリアプランナー、ブロック塀診断士、E&Gアカデミー講師
https://niwatowani.jp/?itemid=120&catid=12