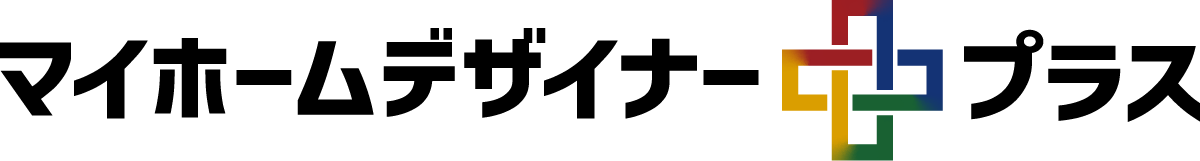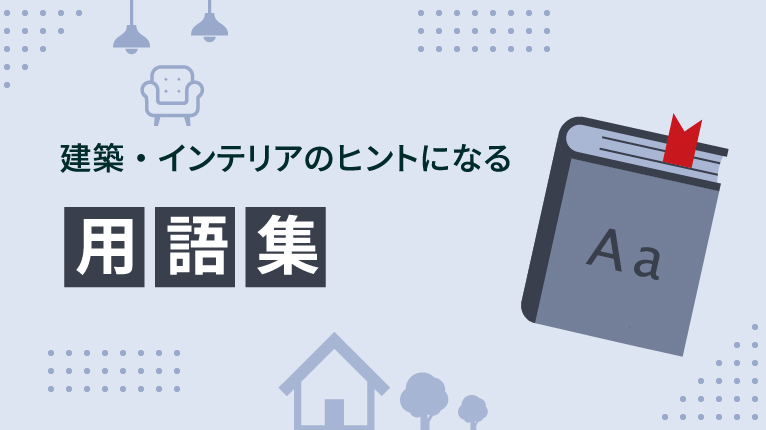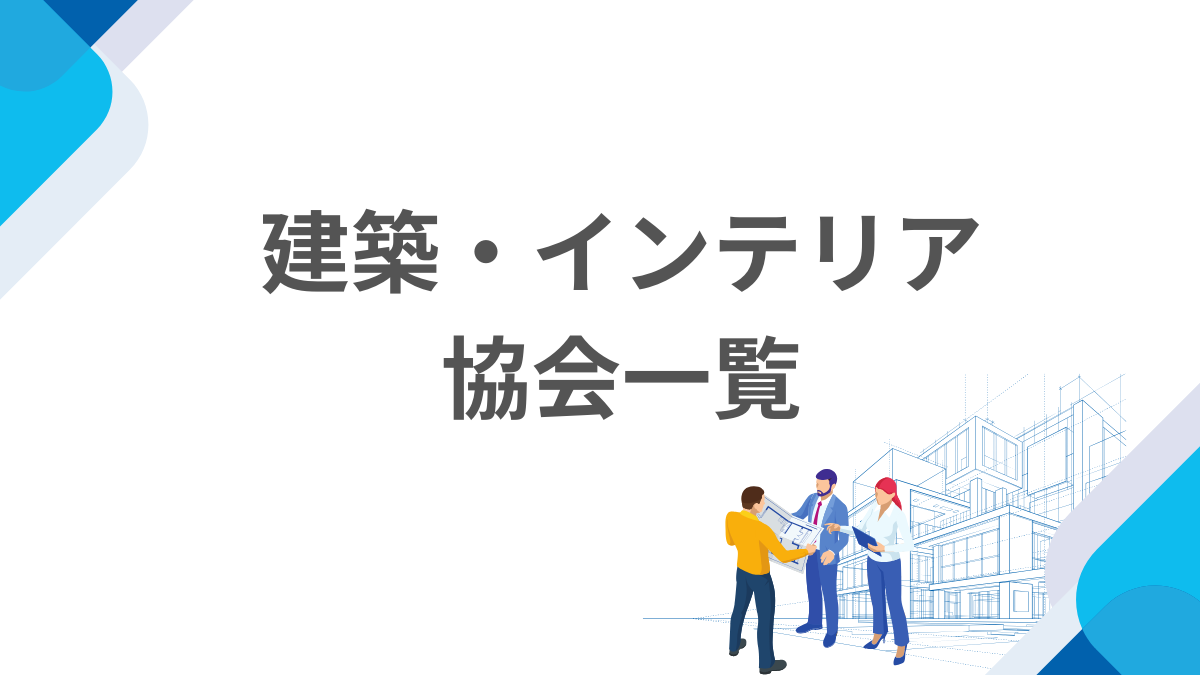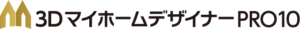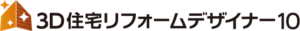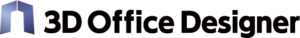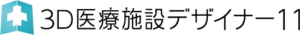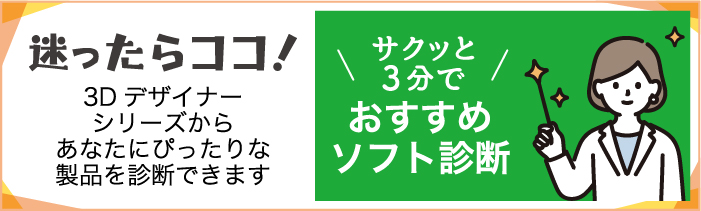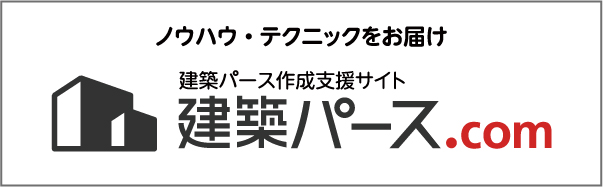人生100年時代の住環境を整える [3]
- 取材

目次
[1]100歳住宅の考え方
[2]20年後を見据えて少しずつがポイント
[3]将来のためにインテリアをどうするかも考えてほしい
「人生100年時代」。厚生労働省もそれに向けた会議を立ち上げるなど、日本の高齢化は進んでいます。
20年前、福祉住環境コーディネーターの資格を取ったことをきっかけに高齢者の住まいとインテリアについての研究を始められた松本佳津氏に、ご自身が提唱する「100歳住宅🄬」について伺いました。
松本佳津 氏:
インテリアコーディネーター&プランナー/愛知淑徳大学・教授/株式会社マツドットコムアイエヌジー
【関連】3Dアーキデザイナー導入事例記事もぜひご一緒にご覧ください。
「変更ありきでスピード勝負。完成形からはじめるインテリア提案に3Dデザイナーシリーズは最適」
――以前100歳住宅について、住宅展示場でお話されたとか。どんなお話をされたのでしょう?
松本さん:
「バリアオフ」をキーワードにして話をしました。住宅はとてもパーソナルなものなので、バリアフリーではなく、その方にとってのバリアをなくすんだという観点で「バリアオフ」とし、一般の方にわかりやすいカラーに関係するお話をしました。
いわゆるバリアフリーというのは物理的な話ばかりになりがちなんですね。
心理的なバリアも原因となるので、個々に寄り添って空間認知を保持するためにバリアを取り除くことを提案しています。
――これは私の経験からなのですが、認知症になると変化に順応するのが難しいから、室内の様子が変わってしまうとその環境に馴染めないんじゃないかと思うのですが?
松本さん:
順応できないことの方が多いです。だからガラッと変えるのではなく、わかりやすくするっていうイメージですね。
その際、60歳代なら20年後、80歳くらいまで自立して暮らせるよう一番重要な空間認知に重点を置きます。インテリアを考えるうえで注目しているのは「反射率」です。具体的には床と壁のコントラストで、反射率30%以上の差をつけるのがポイントです。
全体のカラースキームは日本人の肌の色の反射率を意識します。落ち着く色合いだと思っています。
日本の場合、床が木目で、木製の家具が壁際に並べてあるんです。
ということは、壁と床の境があいまいで、空間の大きさ、広さがわからないか、、もしかしたらどこまでが床かわからなくなってしまっているかもしれませんよね。
わからなければ人間は動けないので、固まっちゃう。
お年寄りの様子を見て「固まってる」って周りは言うけど、実はそれが理由だったりするわけ。

高齢になると、木目の床と木製の家具、境目がわかりにくくなってしまう。
(イメージ/3Dアーキデザイナーの白内障フィルターで出力)
――なるほど、身体機能的に動けないんじゃなくて、怖くて動けないのかもしれないと。
松本さん:
そうです。
ワシントン大学の「シアトル縦断研究」でも空間推論力は進化し続けると報告されているように、きちんと見えてさえいれば認知はできるようになるんだそうです。
日本の場合はわざとわからないようにしてしまっているんじゃないかなと思うんです。
象徴的な話でね、介護施設で白いお皿でカレーライスを出したら、みんなルーしか食べなかったけど、色のついたお皿にしたらみんなご飯も食べるようになったそうなんです。白いお皿とご飯が一体化しちゃってたんですね。
そのくらい区別がわからなくなっていくんです。
反射率と明度は関係するので、単純に明るさの違いが認知できなくなっているんじゃないかもしれないですね。
例えば、光沢のある床とマットな床では同じ色でも違うじゃないですか。でも光沢のある床と白い壁の反射率が同じくらいなら、その境目はわかりにくいんです。
――色の違いだけではないんですね。だとしたら、光の当たり方も影響しそうですね。
松本さん:
そうですそうです。色が変わって見えてしまうのでね。
――じゃぁ、ホントにインテリアの領域なのですね。
松本さん:
日本の住宅の特徴のひとつが、皆さんいろんなものを床に置いちゃうという問題ですね。
日本人は床が汚いっていう認識がないんですね。
――靴を脱いで家に上がるし、床に座るからでしょうか?
松本さん:
中国人の先生に、日本はこんなに洋風が進んでいるのに何でいまだに靴を脱ぐのか?と聞かれたことがあるんです。
中国も元々は靴を脱いでいたんだけど、洋風が当たり前になって靴は脱がなくなったそうなんですね。
考えたこともなかったけど、こればっかりはDNAにしっかり刻まれている気がしますよね。マンションもバリアフリーを意識して玄関の段差がなくなってきているけど「ここから」を明確にしていますよね。
独特の結界発想なんだと思うんです。(笑)

マンションの段差がない玄関(スタッフの自宅)
松本さん:
海外は、自分の部屋だけがプライベートで、それ以外はパブリックスペース。だからみんなのスペースであるリビングに個人のものを置いてはいけないっていう考え方なんです。
日本は玄関入ったら自分たちのスペースって感じで、個人のスペースとの境目はあいまいですよね。
それと、洋風だからスリッパをはいているんだけど、部屋の入り口で脱ぐ人が多い。部屋の中ではスリッパははかないって言う人も結構いました。これも日本の特徴ですね。
――それはフローリングでもですか、畳だからではなくて?
松本さん:
フローリングでも、です。高齢になるといろいろな感覚が鈍ってくるじゃないですか。
足の裏ってずっと何かと接しているので、そこは敏感でいたいっていう気持ちの表れじゃないかなと思うんです。私はこれを「進化」だと思っていて、いろいろ衰えてはくるけれど、それにあがなう術のひとつとして、無意識のそうしている。これは老化ではなく進化です。
――いっぱい物を置いている床を素足で歩くって危険なんじゃないですか?
松本さん:
そう、だからラグとか敷いているの、何枚も(笑)
――あ、わかります、母も1枚では敷き詰められないから何枚も微妙に重ねて敷いてました。「それつまづいて危ないよ」ってよく言いました。
松本さん:
良し悪しですよね。
でも、もともと、スリッパをはく習性がなかったじゃないですか。歳取ってくるとそれが自分たちには培ってきたものが当たり前だと思うので、そうなっちゃうんじゃないかなとも思いました。
――スリッパ…団地ができたときに、PR動画の家族がスリッパをはいていたのがきっかけで、おしゃれアイテムとして広まったって聞いたことがあります。
松本さん:
そう、結局そうなんですよ。見た目で入っちゃってるみたいな。
それは戦争の影響があるなと思っています。戦後の苦しい時代に写真や映像で見た洋風の暮らしがパラダイスのように思えて、憧れて真似したいって思っちゃった。あの暮らしを取り入れれば豊かな気持ちになれるんじゃないかって。

おばあちゃんエリア。座ったままですべてに手が届くようになっている。カーペットは必須。
――子どもの頃に見た欧米の映画やドラマの世界はキラキラして見えました。大きな冷蔵庫から取り出す大っきな牛乳瓶や、オーブンから出てくるご馳走、憧れました。(笑)
なのに畳は手放せないし、玄関では靴脱ぎたいし。日本の住環境ってとっても独特ですね。
ところで、海外にも100歳住宅のような考え方はあるんですか?
松本さん:
イギリス・スコットランドのDSDC(認知症サービス開発センター)が、「認知症のための建築」をまとめたものや「高齢化と認知症のための環境設計評価ツールキット」など、さまざまな資料を出しています。
それを取り入れた介護施設は日本にも何件かありますし、福岡市がDSDCの考え方に基づいた「福岡市認知症フレンドリーセンター」を立ち上げていたりします。
ただ、日本の場合は医療施設や介護施設向けの情報が多くて、住宅についてはまだまだこれからという感じですね。
――私は生まれた時にはもう祖父母が他界していたので、初めての身近な高齢者が自分の両親でした。
わかってあげられなかったことや、想像だにしなかった小さな事件がたくさん起きて、戸惑うことも多かったです。これからは、初めての高齢者が自分という人もでてきそうですし、「知っておく」ことは大切だなと思いました。
松本さん:
今もだけれど、これからはますますそういう人が増えてくるんじゃないかな。
だからこそ、将来のことを考えるときに、暮らす空間が大切なこと、そのためにはインテリアをどうするかも考えてほしいです。
ずっと過ごしてきた自宅で、できるだけ長い時間を自分らしく過ごしたいし、身近な人が希望するならそうさせてあげたいと、ほとんどの方がそう思うわけですから。
――ホントですね。100歳まで過ごせる家「100歳住宅」。基本的なことを知っていれば自分で整えていくことはできそうです。
自分らしく生きることをあきらめずに少し早めに準備を始めるというお話。貴重な気づきをありがとうございました。