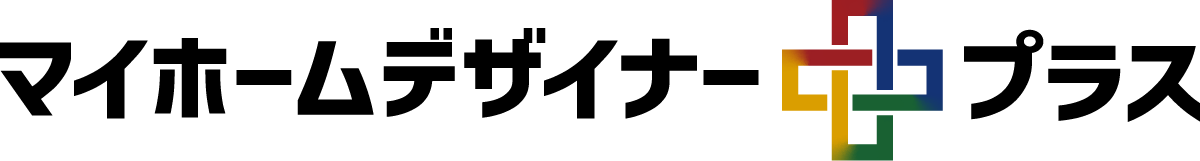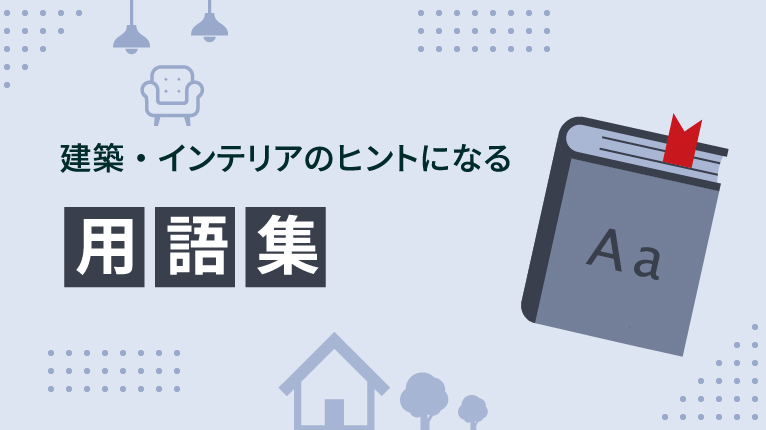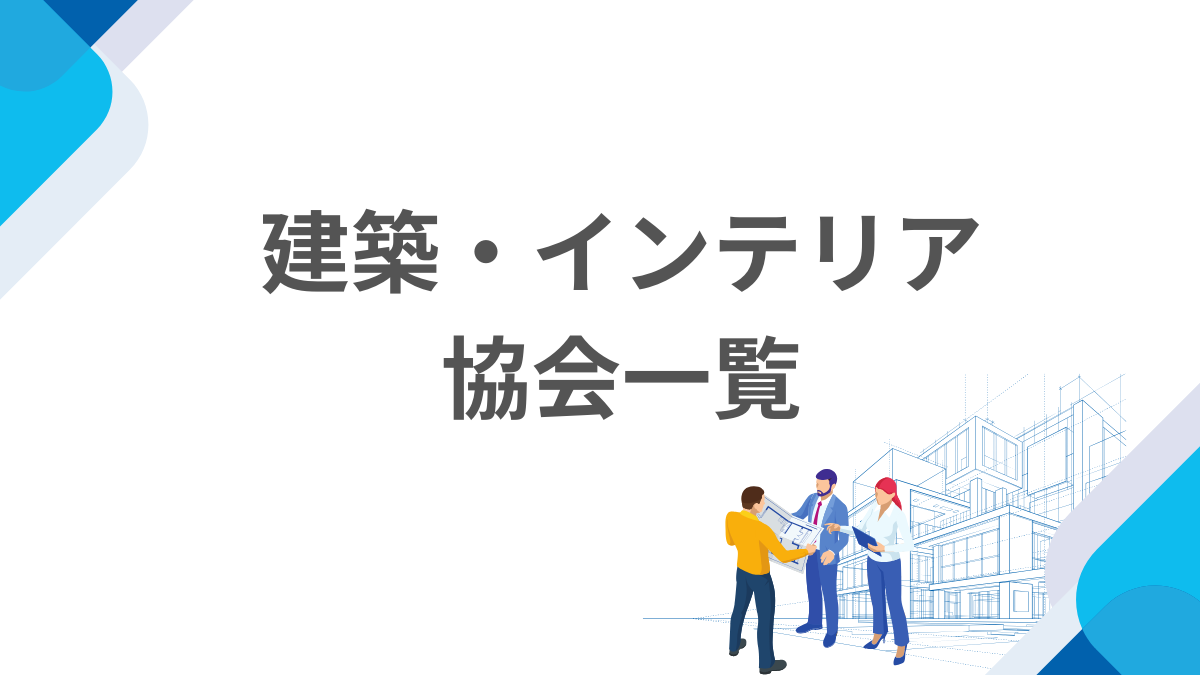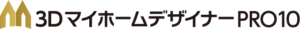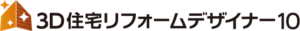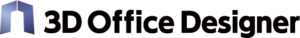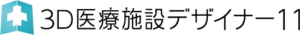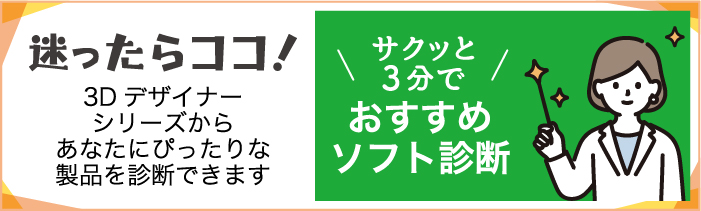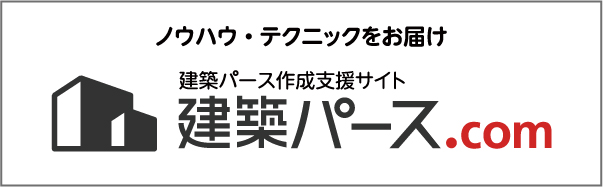作業療法士ICが伝える部屋別チェックポイント 55歳からのインテリアの作り方【階段】
- お役立ち

キケンエリア「階段」 ~絶対にころびたくない場所!階段のはなし
まずは、転倒事故として一番危険なにおいがする階段のお話しから始めましょう。
最近は建築基準法で決められているので、新築の家は階段に必ず手すりがついていますが、古いお家にはついていないことがあります。そしてそんな手すりのない古い家の階段ほど、勾配急で危険なにおいがするのです。
階段の手すり
私の実家も築50年なので、階段には手摺はありませんでした。
ところが、久々に帰省したら、足腰が弱ってきて不安を感じた父がDIYで手すりをつけていました。
それがこの写真です。
これは私たち作業療法士からしたら突っ込みどころが満載の残念な階段なのですが、さて、皆さん、この階段の残念ポイント、わかりますか?

この階段の残念ポイントはこちら。
①右側だけに手すりがある
手摺は階段幅が広ければもちろん両側につけるのがいいのですが、階段幅が狭いなど、片方にしかつけられない場合もあります。ではその場合は、どちら側に付けるのが良いか。
それは、「降りる時に利き手側につける」です。
両親は右利きなので左側に付けるのが良いのです。
②手すりが途中で切れている
実家の写真のように階段の途中で手摺が切れているのは大変危険。上から下まで通してつけるようにしてください。
③手摺の端の扱い
さらにもう一つ、見落としがちなところが、手摺の端の扱いで、必ずエンドブラケットをとりつけるようにしてください。
エンドブラケットとは手すりの一番端に取り付ける、壁側に“くにゅっ”と曲げるブラケットのことです。
実はあの「くにゅっ」がとても重要で、何かの拍子に洋服の袖口が手すりに引っかかるのを防いでくれます。
ということで、こちらが正解です。

一般に、手摺の高さはおおよそ75~80cmくらいが使いやすい高さと言われています。
実家の手すりは私には少し低すぎる位置でしたが、母の身長が低いのでちょうどよい高さと言えます。
このように個人宅の手すりの高さは、通り一辺倒ではなく、使う人にあわせて一番力の入りやすい高さに決めるのが正解です。

階段の床面
そして最後に。
安全な階段にするには、滑りにくいこと、そして冷たくないことが大切です。
床が冷たいとスリッパをはく人が多いから、というのが理由です。
足腰が弱っている人がスリッパを履いて階段の上り下りをするのは大変危険です。

こちらの写真は80歳のおばあちゃまのお一人暮らしのお宅。間取の加減でどうしても二階にしか寝室が作れず、毎日階段の上り下りが必要でした。そこで、手すりの設置に加えてニードルパンチカーペット(不織布/フェルト製のカーペット)敷きに変更させていただきました。
おばあちゃまには、
「はだしでも快適、そして滑りにくい!」
と大変喜んでいただきました。
もくじ
| 1.序章 ~家の中には危険がいっぱい |
| 2.キケンエリア「階段」 ~絶対にころびたくない場所!階段のはなし |
| 3.家の顔「玄関」 ~上がり框・アプローチ・手すりのはなし |
| 4.転倒が多い「トイレ」 ~大切な4つのポイント |
| 5.事故多発エリア「お風呂」 ~リラックスは大事、でも安全性はもっと大事! |
| 6.リビング ~ラグを敷く?敷かない?つまづきのはなし |
| 7.ダイニング ~”つまる”と座位姿勢のはなし |
| 8.寝室 ~カーペットのはなし |
執筆者紹介
松本 理絵 氏
作業療法士(国家資格)
インテリアコーディネーター/二級建築士
有限会社宮本家具工業所 副社長
Web
公式:トータルインテリア専門店 ミヤカグ
インスタグラム も更新中
広島県インテリアコーディネーター協会 副会長

広島大学医学部保健学科を卒業し、広島市内にて作業療法士として病院で高齢者のリハビリの仕事に従事。
その後、結婚を機に夫の家業である家具製造販売会社に入社。
入社後インテリアコーディネーター資格、二級建築士資格を取得し、現在では「広島一敷居の低いインテリアコーディネーター」をキャッチコピーに、お客様の生活空間を豊かにするためのインテリアを提供している。
「元医療職をいかして、目の前の困っている人のニーズをしっかり拾って寄り添ったリフォームやアイテム選定など心がけています。」