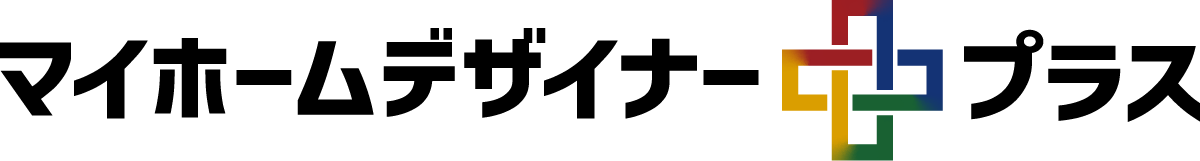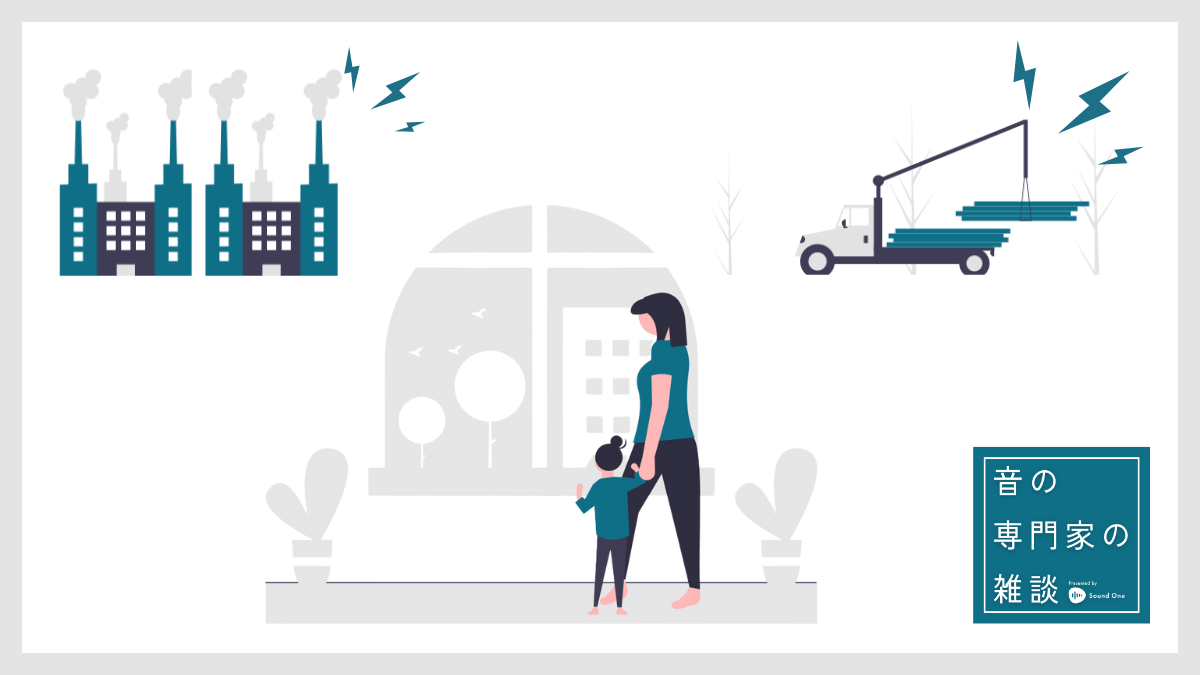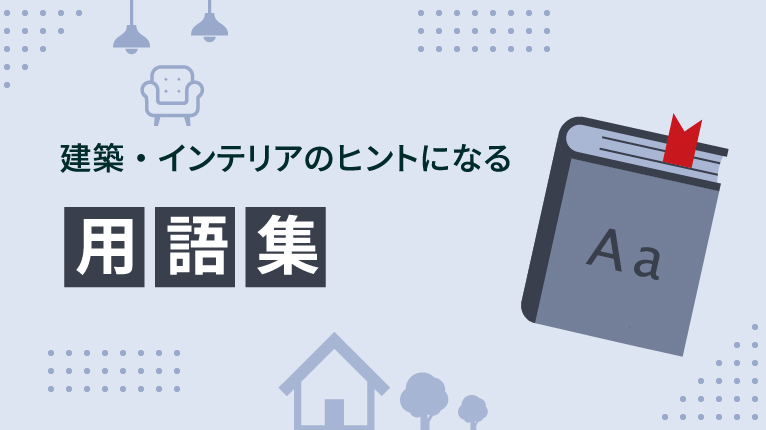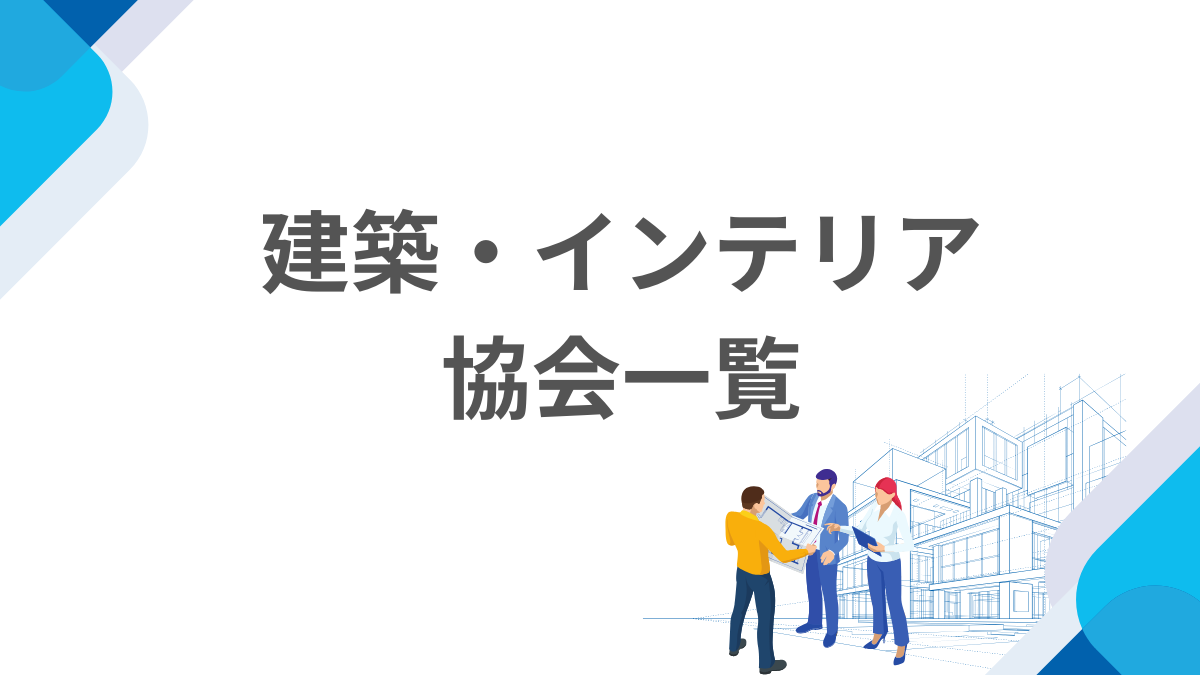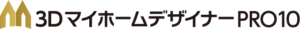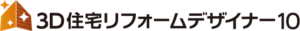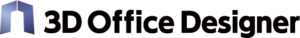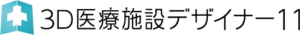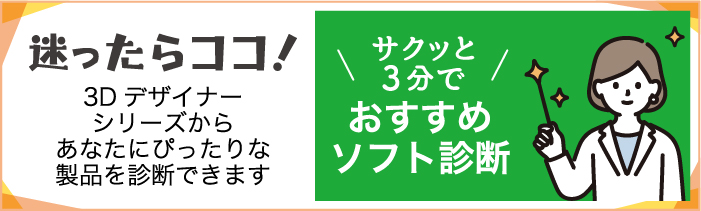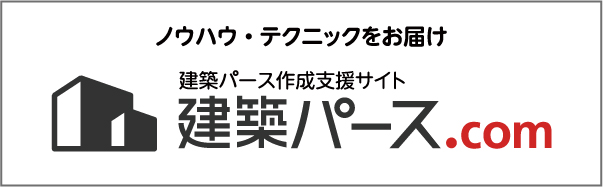【第3回】音の専門家の雑談「騒音ってどんな音?(子どもの声は騒音か)」~分かり合えなくても分かり合うための努力をすること~
- お役立ち
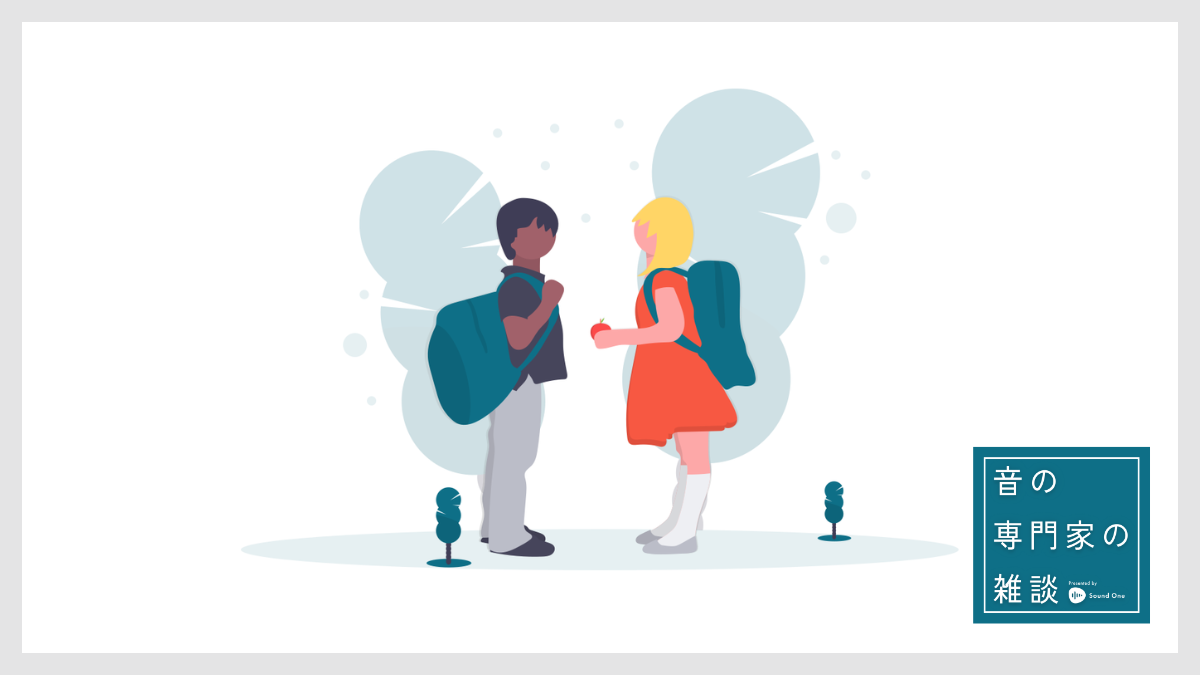
住宅地や集合住宅で、トラブルになりがちな騒音問題。
音の専門家はこの問題をどう捉えているのでしょうか。音に特化したサービスを提供する株式会社Sound Oneの石田康二さん、楠美貴大さんが「騒音ってどんな音?(子どもの声は騒音か)」をテーマに、音と地域コミュニティの関係について掘り下げます。
当記事は、株式会社Sound Oneが配信するポッドキャスト『音の専門家の雑談』から抜粋、編集しています。全文は、ポッドキャストで軽快なトークとともにお楽しみください。
音の専門家の雑談 Presented by Sound One #94【騒音ってどんな音?(子供の声は騒音か)】
人物紹介
株式会社Sound One 取締役 石田康二
40数年間「音」を探求しています。研究、ビジネス、趣味の対象でもあり、人生の大半、音のことを考え、関わってきました。今は、GoogleやAIで、誰でもすぐに正解に辿りつける時代。
「知ること」より「感じる」こと、「はかること」より「はかないこと」を大切にしたいと思う今日この頃です。

株式会社Sound One セールスマーケティング チームリーダー 楠美貴大
音の回路設計やマイクの企画、開発、商品化設計に携わり、現在は、Sound OneサービスのセールスマーケティングやPodcastコンテンツの運営を担う。
好きなもの:歌、歴史(特に戦国時代)、パグ
好きな瞬間:考え方や概念が繋がって、自分の世界観が拡がるとき
人生のテーマ:「あらゆるシーンにユーモアを」

分かり合えなくても分かり合うための努力をすること

マンションなどの集合住宅の場合は、人間関係を構築するのは不可能なことではないような気もするんですが、例えばニュースでよく見る「子どもの声がうるさいと近隣から反対意見があり、幼稚園を建てるのやめました」みたいなケースもありますよね。
「子どもの声はうるさい」と言っている個人とその対象の距離感っていうのは、人間関係よりも、もう少し距離があるというか・・。
ものすごくありますね。
「人間vs人間」ではなくて、「施設vsコミュニティの住人」とすると、関係性をどうやって作っていくかっていうのはすごく重要。
幼稚園と関係ない人たちも、周囲に住んでるわけだよね。
昼間仕事で外に出ているような環境の人とは、あんまり問題が起こらないのかもしれないけど、例えば文筆業みたいな人が家の中で、どうしても子どもたちの声が煩わしくて集中できないとか、いろんな事情があるわけじゃないですか。病気で寝たきりで、声に対する感度がすごく高くてストレスを感じる人もいるかもしれない。
そういうところまで考えるとすごく難しいんだけども、仮に幼稚園だとすると、例えばお迎えの車のアイドリングの音がうるさいとか。幼稚園の送り迎えをするお母さん、お父さんたちが子どもを待ってる間に外で大きな声で笑い話をするのがうるさいとかね。いろんな要素があるわけです。


確かに。子どもの声だけじゃないですね。
うん。渋滞を起こして、車で通行するのがすごく不便だとか、いろんな周辺の問題っていうのも含まれるわけですよ。それに対して苛立つ人もいるわけだよね。


なるほど。
どちらかというと僕は、そんなこと気にしないでコミュニティに子どもたちを育む環境を作れた方が絶対いいわけだし、運動場に出て大きな声でわあって叫ぶみたいなことだって許されるべきだと思う派なんだけど。
でも、専門家としての立場でその両方を見たときに、「100%こうだ」っていうことがなかなか言えない難しさがある。


そうですよね。私も、石田さんのように子どもの声で活気がある方がいいじゃないって思っちゃうんですけど。
でも、対極にいる方々の困りごとにも触れると、ちょっと揺らぐというかどっちとも言えないよなっていう気持ちになるかもしれないですね・・。
だから、最初がやっぱり大事で。
いろんな住人が住んでいるので、応援してくれる人もいれば、心の中では精神的な苦痛を与えている可能性がある。
幼稚園側も、そういう人たちが周りに住んでるんだという認識に立って、例えば、住民に対して説明をしっかりするだとか、子どもの声は仕方ないにしても、大人たちにはちゃんと配慮させるだとか、できる限り車では迎えに来ないとか。
いろんな努力することが、周りの住民も「しっかりやってくれてるんだったら、多少は我慢しなきゃ」と折り合いをつけられるんだけども、当たり前のように「これは権利です」みたいな形でやってしまうと、そこから問題が大きくなる。


確かに。割と情緒的に「自分が“ないがしろにされてる感”」になると、入り口から感じ方が変わってくるのかもしれないですよね。
うん、音の大きさじゃないんですよね。
もちろん、きっかけではあるんだけども、それだけではないし、むしろそれ以外のことが関係を悪化させてるっていう気がする。


なるほど。
そういうのをNIMBY(ニンビー)問題ってよく言われるんです。
Not In My Backyard。廃棄物の処理場だとか、お葬式を挙げる斎場だとか。どちらかというとネガティブに見られがちなものを、自分の隣の敷地に建ててほしくないっていう。


ごみ処理場とか。絶対、社会に必要なんだけど、自分の家のバックヤードには建ててほしくないなっていうことですよね。
NIMBY(ニンビー)
「Not In My Backyard(自分の家の近くには置かないで)」の略。
公共に必要な施設であることは認めつつも、自らの居住地域には建てないでくれと主張する住民たちや、その態度を指す言葉。例として、原子力発電所、廃棄物処理施設、火葬場、幼稚園、ダムなどが挙げられ、衛生・環境・騒音への影響や治安悪化の懸念が理由とされている。
こういう子どもの問題っていうのは昭和の時代はあんまりなかったんだけど。


確かに。なんとなく、徐々に厳しくなってきたイメージがあります。
そうそう。
最近、都市に人口が集中して、待機児童がたくさんいるわけです。
だから、どうしようもないロケーションで保育園や幼稚園を建てなきゃいけないっていう事情があったりするわけですね。


駅近のビルの1階に建っていたりとか。
ちょっと狭すぎないかっていう印象を持っちゃうところもあるんですけど。
でも実際、待機児童の保護者の方々にしてみれば、それでもあったほうがありがたいっていうことなんでしょうね、きっと。
だから、ロケーションに困って、密集した住宅地域の残された土地に保育園とかを建設すると、たちまちそういう問題が起きてくる。
まあ、昭和の時代はおおらかだったっていう面もあるんだろうけども。
じゃあ、国が違えばどうかっていうと、国際的にもそういう問題がある。


あ、そうなんですか。
うん、ドイツもずいぶんと問題が起きてたらしいんですよね。


なんとなく日本は土地が狭いとか、住んでる距離感が狭いから、そういう問題があるのかなって思ってたんですけど。
僕もそう思ってたんだけど。
ドイツでは2011年に、国の法律で「子どもの声は騒音ではない」と決まった。


「子どもの声は騒音ではない」という法律って、法律を守る側からするとどういう守り方すればいいのか、ちょっとピンとこないんですけど。
「聖なる騒音」っていう言い方もあるんだけど、幼稚園でどんなに大きな声を張り上げても、子どもたちの声はそういうふうに受け取れと。それをコンセンサスにしたわけだよね。


つまり、子どもの声が騒音っていう訴えは受け入れないよっていうことですね。
そういう海外の事例もあって、4年遅れで東京都も条文で騒音の規制対象からは外したんです。


そうなんですか?
規制対象からは外したけど、受忍限度っていうものは残ったんですね。
だから、子どもの声を数値的に規制することはできないけれども、
騒音出す側(エミッション)と受け取る側(アイミッション)の関係で、受け取る側の状態や環境を鑑みたときに「これは受忍限度を超える」という判断もできるわけです。
だから幼稚園側が訴訟に負けるっていうケースだってあるわけですよね。


なんとなく、ニュースを見てると幼稚園側が勝ってる様子が見られないというか。
うん、だから防音壁立てたりとか、建設中止になったりとか、よくあるよね。
僕が私淑と仰ぐ一人の内田樹(ウチダ タツル)さんっていう人が、地域コミュニティの話をされていて。いかに成熟していくかっていう文脈でいろんなことを語ってるんだけど、すごくいいなあと思ったのが、「集団のすべての構成員は、時間差をともなった『私の変容態』である」って言い方をしてますね。


ああ、なるほど。
子どもたちは過去の自分だし、お年寄りは未来の自分だっていうことですね。
まさにそう。だからそういう地域のつながりを持てば、子どもたちに対してちゃんと育ってほしいっていう期待だとか、お年寄りに対するケアだとか。
自分はかつてそうだったし、これからそうなるんだ、自分と同じなんだっていう見方を地域の人たちができれば、地域として成熟していけるんじゃないかみたいな。
すごくいい話だなと思ったのね。


それ、わかりますね。
複雑さを増す騒音問題ですが、第4回では地域コミュニティの行動を変えるためには何が重要か、迫っていきます。お楽しみに。
【第4回】「連綿と続く流れの中にいる自分」はこちら>>
プロフィール

株式会社 Sound One
音・振動分野の電子計測機器や試験機の開発を行う株式会社小野測器のグループ会社。
音を聴いた印象を評価するWebアンケートサービス「Sound One」の開発、運営を行っています。
Sound One 公式サイト
https://soundone.jp/
【異音の問題をスピーディに解決】音のWebアプリケーション
https://sound-one.net/lp/abnormal-noise/