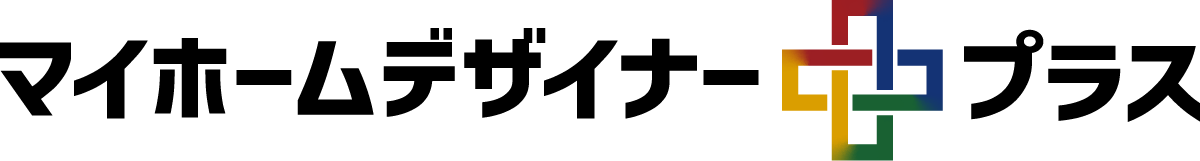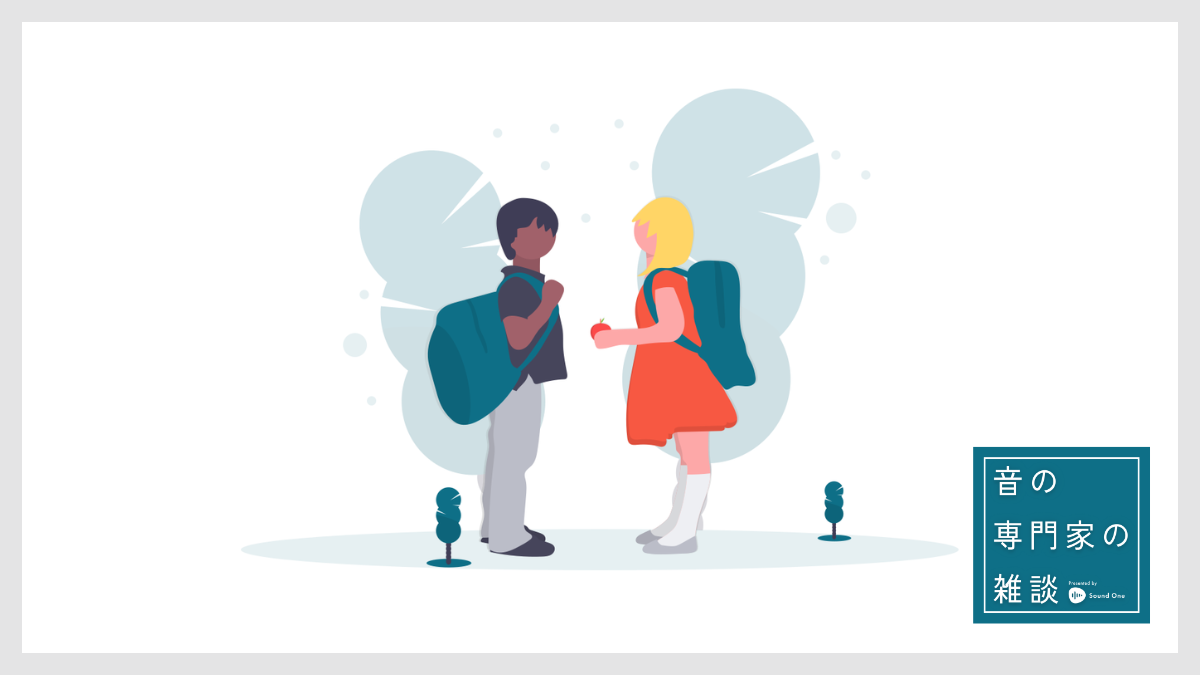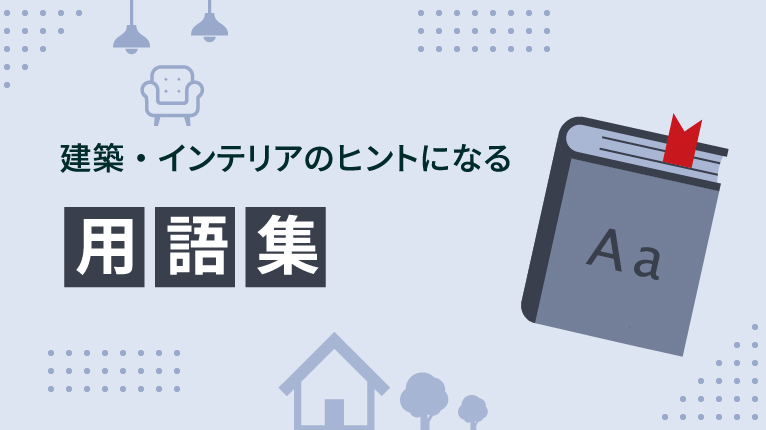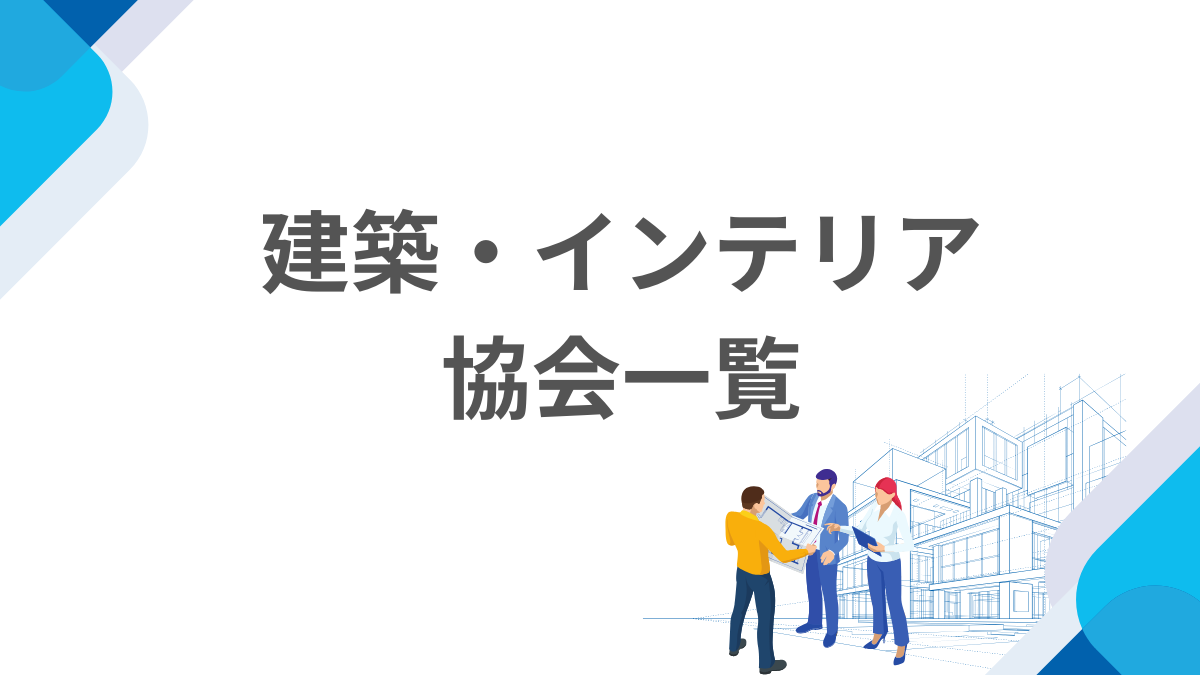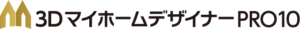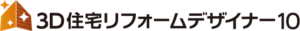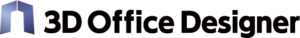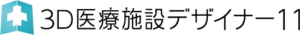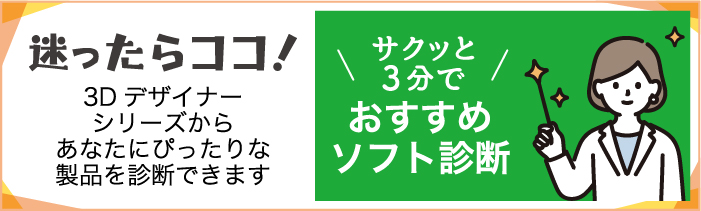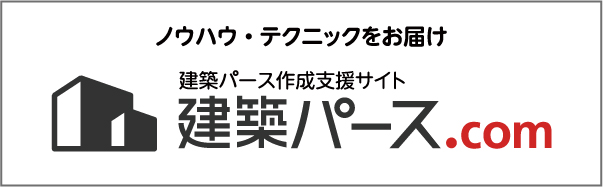【第6回|最終話】音の専門家の雑談「騒音ってどんな音?(子どもの声は騒音か)」~身の周りに、技術で工夫できることはまだある~
- お役立ち
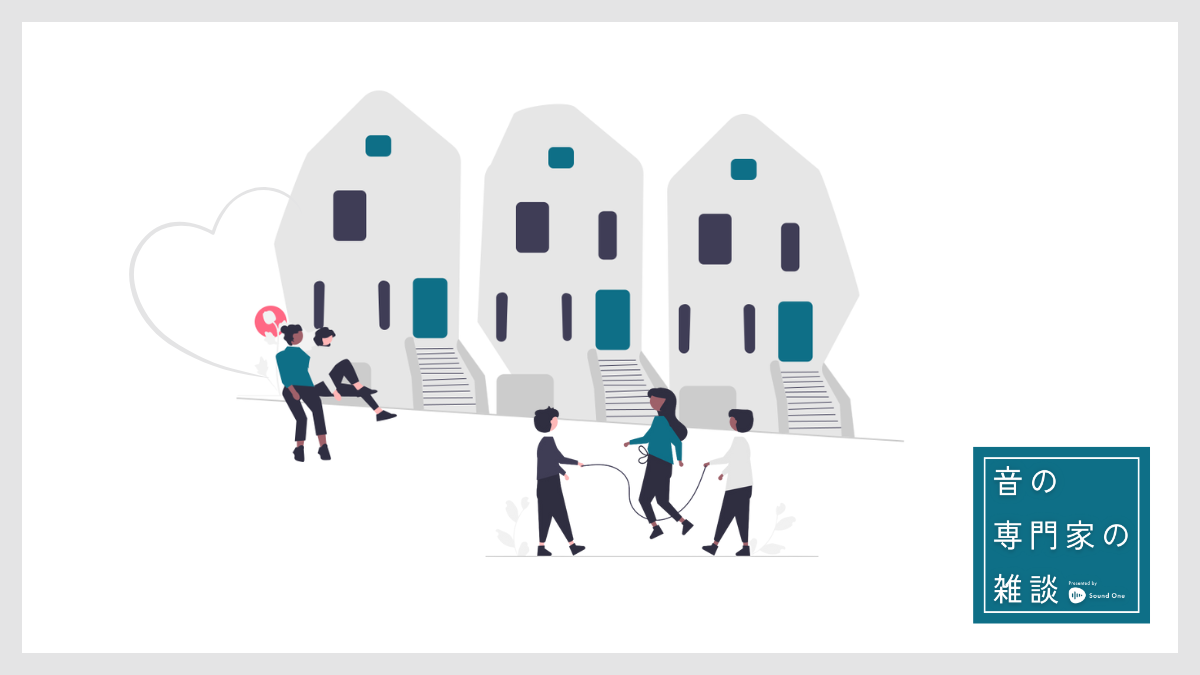
住宅地や集合住宅で、トラブルになりがちな騒音問題。
音の専門家はこの問題をどう捉えているのでしょうか。音に特化したサービスを提供する株式会社Sound Oneの石田康二さん、楠美貴大さんが「騒音ってどんな音?(子どもの声は騒音か)」をテーマに、音と地域コミュニティの関係について掘り下げます。
当記事は、株式会社Sound Oneが配信するポッドキャスト『音の専門家の雑談』から抜粋、編集しています。全文は、ポッドキャストで軽快なトークとともにお楽しみください。
音の専門家の雑談 Presented by Sound One #97【騒音ってどんな音?(子供の声は騒音か)】
人物紹介
株式会社Sound One 取締役 石田康二
40数年間「音」を探求しています。研究、ビジネス、趣味の対象でもあり、人生の大半、音のことを考え、関わってきました。今は、GoogleやAIで、誰でもすぐに正解に辿りつける時代。
「知ること」より「感じる」こと、「はかること」より「はかないこと」を大切にしたいと思う今日この頃です。

株式会社Sound One セールスマーケティング チームリーダー 楠美貴大
音の回路設計やマイクの企画、開発、商品化設計に携わり、現在は、Sound OneサービスのセールスマーケティングやPodcastコンテンツの運営を担う。
好きなもの:歌、歴史(特に戦国時代)、パグ
好きな瞬間:考え方や概念が繋がって、自分の世界観が拡がるとき
人生のテーマ:「あらゆるシーンにユーモアを」

身の周りに、技術で工夫できることはまだある
幼稚園のNIMBY問題に戻ると(※第3回参照)、例えば小学校も幼稚園も最近、運動場が狭くなってきて、なかなか運動会ができないみたいな。
でも、運動会の練習の声よりも、むしろ太鼓の音だとかスピーカーからの音声、先生の指導の声がかなり大きく響いて、それがクレームになるっていうケースがある。
でも、技術的にラッパスピーカーが下に向いてなくて広域に向いてたりするんだよ。
そういうちょっとした工夫で数デシベル下がればだいぶ違うんだろうなと思うんだけども。


なるほど。
あとは、ビリついたスピーカーをそのまま使ってるだとかのメンテナンス。
お父さん、お母さんになにがしかその関連の人がいる可能性は低くはないと思うので、そういう地域住民たちが技術的なサポートにまわるだとかね。
地域全体で知を集めて、問題になる前に解決するような仕組みみたいなのができないかなとか思ったりする。


知らないだけで、実は技術的に軽減できたり、低減できたりするものってありそうですよね。
だから、「技術的に改善しましたが、前と比べてどうでしょうか?」みたいなコミュニケーションが住民と取れると、「ここまで(改善を)やってくれてるんだったら、多少我慢しようか」っていう気にもなるよね。


そう思います。
ちゃんと、そのアプローチ・プロセスも共有すれば、住民の“ないがしろにされている感”の感じ方は変わりそうな気がしますよね。
結果だけを共有っていうより、プロセスを共有するっていうのは大事かもしれないですね。
そう考えると、音の問題だけではなくて、地域にはいろんな専門家が住んでるわけじゃないですか。
その専門家は、自分の仕事場に行って専門性を発揮してるわけだけども、地域住民に戻れば、あたかも専門性を全く失ったように生活してるわけだよね。


確かにそうですね。
これもったいないよね。そこをうまく活用していく。


スキルって切り口だけじゃなくても、例えばコミュニケーションとか。
そういうソフトスキルみたいなものもコミュニティに役立てられる、貢献できるシーンはありそうですよね。
って言いながらも、あんまり自分の住んでる場所のコミュニティに興味を持ったことないから反省ですね。どうすれば興味を持てるんだ?
・・難しいよね。


困ってるっていうのを地域がもっと発信していいのかもしれないですね。
そうすると、自分の持ってる何かをここに役立てられるかもしれないっていう想像力が働くかもしれない。
うん、僕ね、20年ぶりに町内会の理事をやってるんだけど。
やることが20年前と全く変わってないんですよ。
例えば、夏休みのラジオ体操のスタンプを押してやる役だとか、冬になると火の用心とか。
それから公園の清掃、正月のどんと焼き、消防士さんを手配したりとか。
マニュアルがあるんだけど、20数年間全く変わってないですよ。


そうなんですか!?
いや、変わらないことはいいことかもしれないんだけど、世代は変わってるわけですよ。
そこにおける町民のニーズはかなり変わってるはずなんだけど、マニュアルは全く変わってない。
やり続ける意味があるものもあるからいいんだけど、そうじゃなくて代々同じことをルーチン的にこなしてるっていう感じなんだよね。
これで街の成熟に向かうのかな?っていうのが最近の関心。


20年間変わってないって意外ですね・・って言いながら、
自分の故郷も同じ状態の気もしますけど。
変わらない良さっていうのももちろんあるはずで。祭りだとか。
ラジオ体操もいいと思うんだよ。子どもたちが集まってくれて、体操してスタンプ押して、みたいな習慣は残していってもいい事だと思うんだけど。
徐々に町内会から抜けていく人が増えていって、ほんの一握りの人たちがそれをやってるっていうことが負担になり、だんだんその人たちも年をとって。
世代交代するかっていうと、子どもたちはみんな違う場所に出て行って住んでるわけだから、どんどんそういうコミュニティの親密さみたいなものがなくなっていくのに、行事だけこなしていていいのかなっていう。


ああ、なるほど。
確かに「子どもの声を騒音って感じる」という話も、勝手な予想ですけど、子どもたちと一緒に過ごすっていう共通の体験をすることで、感じ方も変わりそうですよね。
だから、もしかしたら騒音対策としては、いろんな世代が交わる機会を作るとか、そういう方が騒音対策になったりとか。
そうですね。十分なると思いますね。
だから、そういう意味でどんと焼きとかラジオ体操とか、そういうのはやったほうがいいのかもしれない。


確かに、祭りって今も淘汰されずに残ってますね。
祭りって、縦のつながりを感じるというか、気づかされる一つのイベントになるんですよね。
まさにそうだよね。


先輩から後輩にアナログ的に受け継ぐものの一つかもしれないですね。
全6回にわたり、音の専門家によるトークをお届けしました。
騒音は、簡単に解決できない問題である一方、私たちの社会や文化、さらにはコミュニティ内の人間関係を映し出す鏡でもあります。今回のトークを通じて、地域に関心を持ち、互いに寛容であることの大切さを学ぶ機会となりました。
騒音を単に「煩わしいもの」として排除するのではなく、その背後にある地域コミュニティの在り方や価値観に目を向けることで、音を共有し受け入れる豊かな社会を目指していきたいですね。
プロフィール

株式会社 Sound One
音・振動分野の電子計測機器や試験機の開発を行う株式会社小野測器のグループ会社。
音を聴いた印象を評価するWebアンケートサービス「Sound One」の開発、運営を行っています。
Sound One 公式サイト
https://soundone.jp/
【異音の問題をスピーディに解決】音のWebアプリケーション
https://sound-one.net/lp/abnormal-noise/