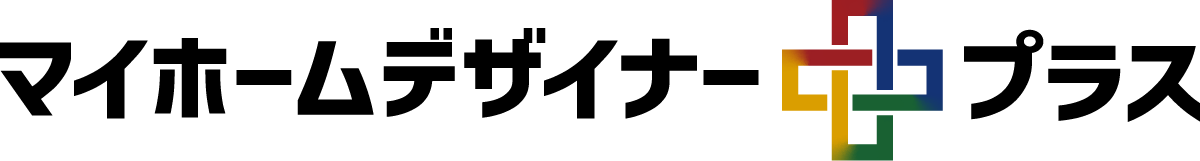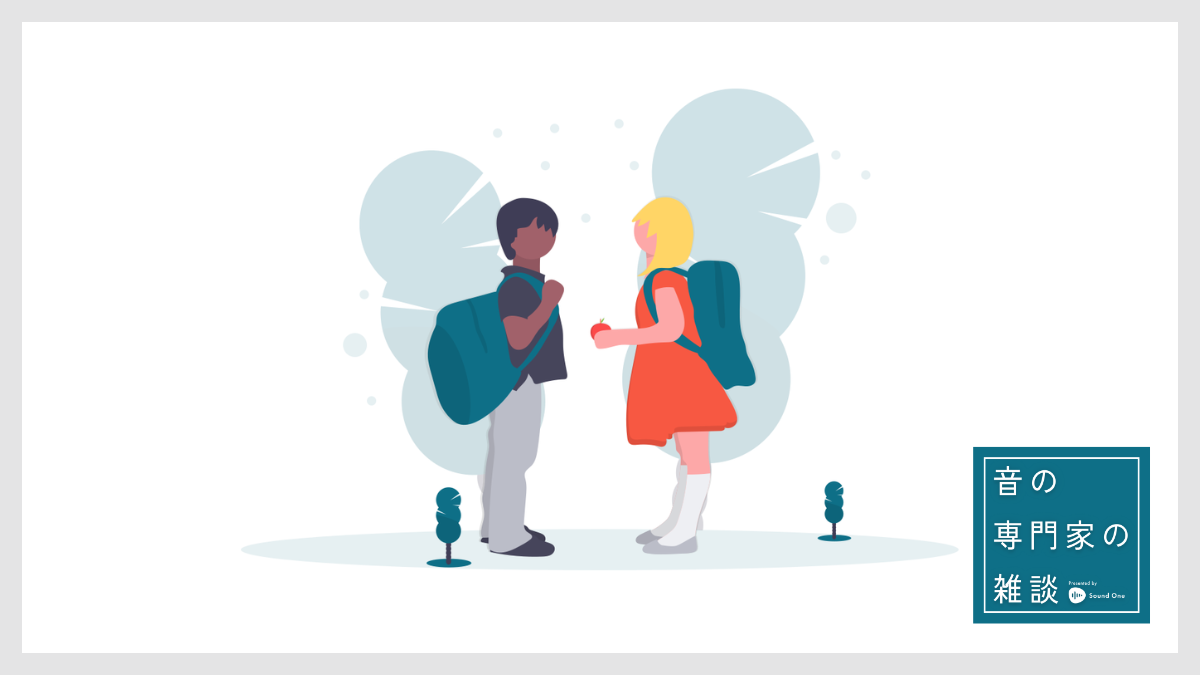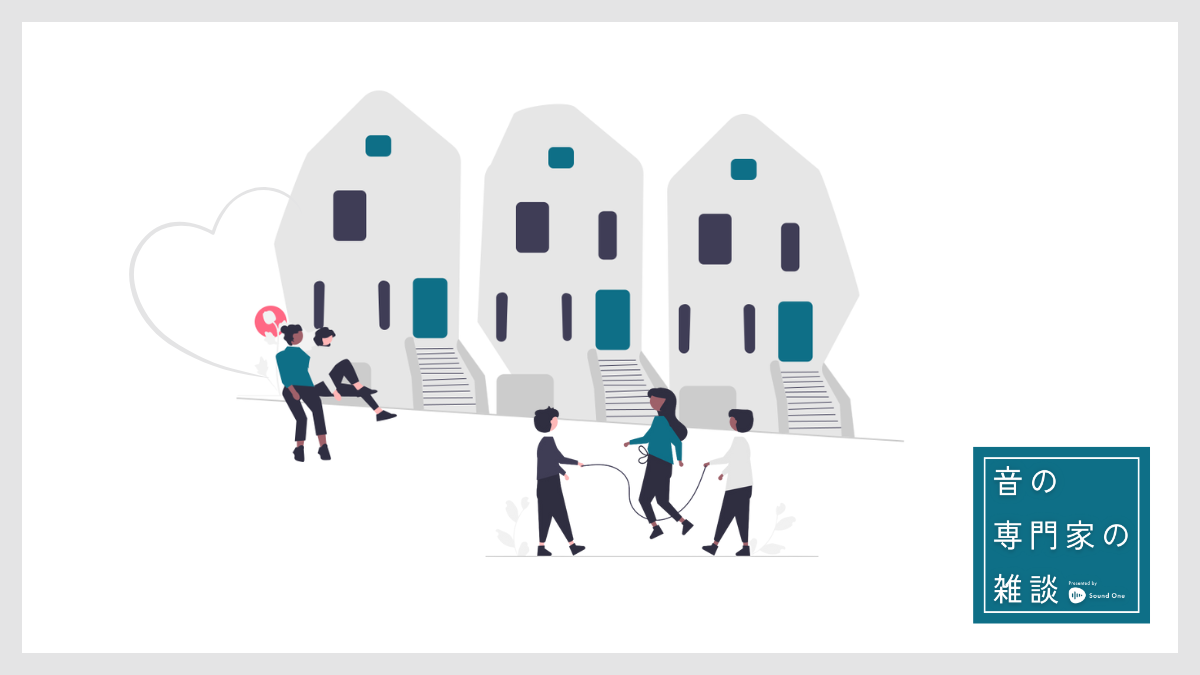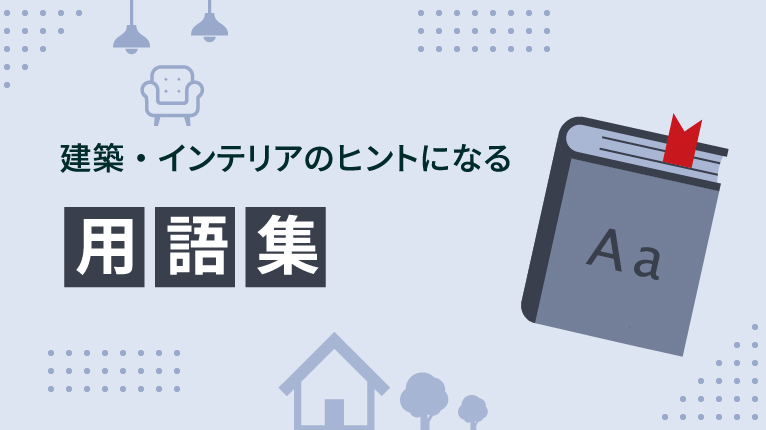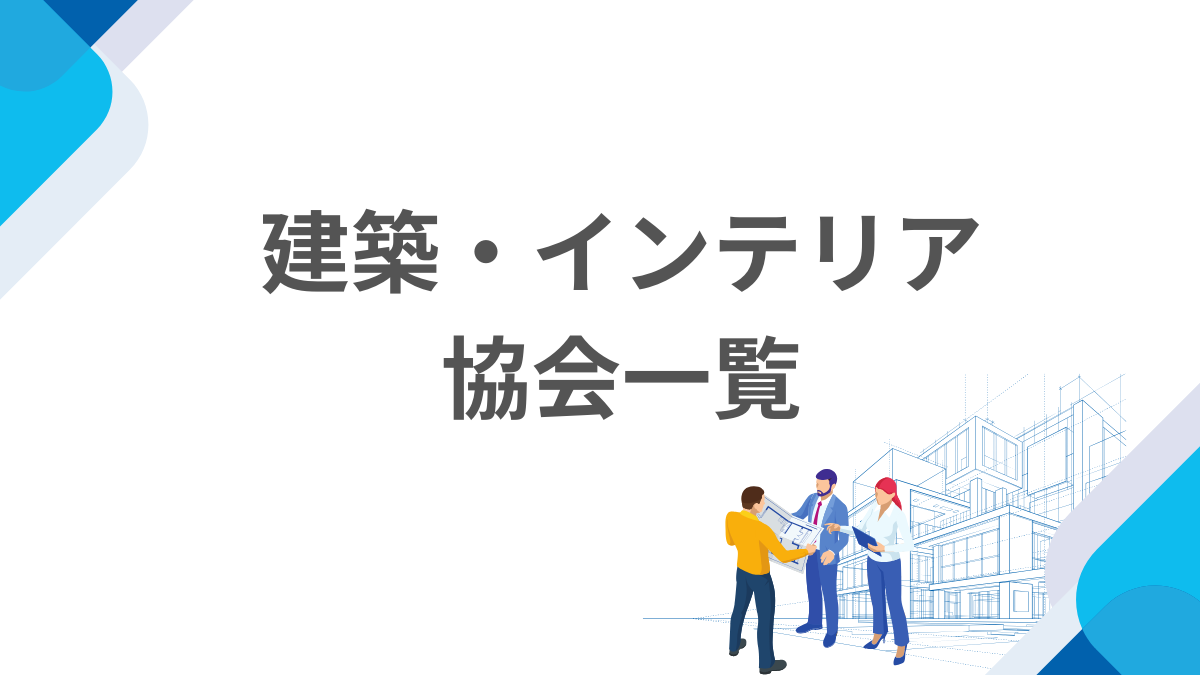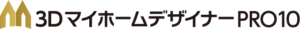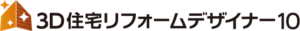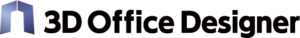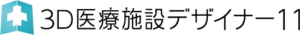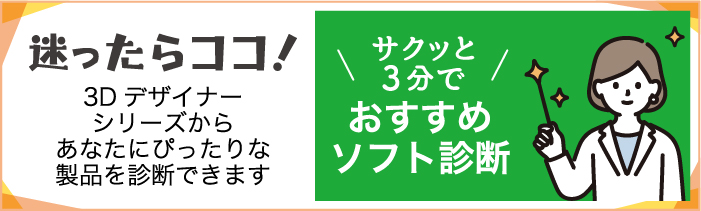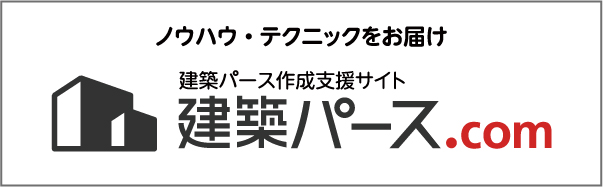【第5回】音の専門家の雑談「騒音ってどんな音?(子どもの声は騒音か)」~人との距離感が寛容さに影響する~
- お役立ち

住宅地や集合住宅で、トラブルになりがちな騒音問題。
音の専門家はこの問題をどう捉えているのでしょうか。音に特化したサービスを提供する株式会社Sound Oneの石田康二さん、楠美貴大さんが「騒音ってどんな音?(子どもの声は騒音か)」をテーマに、音と地域コミュニティの関係について掘り下げます。
当記事は、株式会社Sound Oneが配信するポッドキャスト『音の専門家の雑談』から抜粋、編集しています。全文は、ポッドキャストで軽快なトークとともにお楽しみください。
音の専門家の雑談 Presented by Sound One #96【騒音ってどんな音?(子供の声は騒音か)】
人物紹介
株式会社Sound One 取締役 石田康二
40数年間「音」を探求しています。研究、ビジネス、趣味の対象でもあり、人生の大半、音のことを考え、関わってきました。今は、GoogleやAIで、誰でもすぐに正解に辿りつける時代。
「知ること」より「感じる」こと、「はかること」より「はかないこと」を大切にしたいと思う今日この頃です。

株式会社Sound One セールスマーケティング チームリーダー 楠美貴大
音の回路設計やマイクの企画、開発、商品化設計に携わり、現在は、Sound OneサービスのセールスマーケティングやPodcastコンテンツの運営を担う。
好きなもの:歌、歴史(特に戦国時代)、パグ
好きな瞬間:考え方や概念が繋がって、自分の世界観が拡がるとき
人生のテーマ:「あらゆるシーンにユーモアを」

人との距離感が寛容さに影響する

第3回で騒音に関するドイツの法律の話がありましたが (※第3回記事)、例えば他の国だと違うよみたいな話ってあったりするんですか?
どうなんだろうな。
僕、インドには3回ぐらい行っていていろんな場所を回ったんですけど、すごく人と人の距離が近いんですよね。接近するんです。物理的に。例えば、買い物やスタバでコーヒーを注文するために並んでる時にもこんなに近寄るの?みたいな感じなんです。
東南アジアの特徴だけど、声も大きくて至るところでクラクションが鳴るし、騒音レベルってめっちゃ高いんですよ。一方で、フィンランドとか北欧は、人と人の距離感はすごく遠い。


へぇ~!
それをね、「プロクセミクス」っていうエドワード・ホールの造語があって。
例えば椅子を並べる時にどれぐらいの感覚で並べるかだとか、人が並ぶ時にどれぐらいの間隔で並ぶかみたいなところは、文化によって違うと。
まさに僕は北欧とインドで経験したんで「なるほどな」と思ったんだけど。


なるほどなるほど。
インドは、ものすごい近距離でわあっと喋るから、町全体がワイワイしてるわけですよ。
人口が、14~15億人いるから都市に行けばなおさら。
だから、騒音に対する耐性があるっていうか、騒音のクレームってあまりないんじゃないかなって、想像だけど。そういう環境にいるから当たり前っていうかね。
だから、騒音文化っていうのは、国民性だとか、経済的な環境だとか。
そういうものに結構リンクしていくんじゃないかなと思います。
あとは、歴史的な話にもなるけれども、イザベラ・バードが明治時代に日本で旅行した時に、隣の部屋とふすま一枚の旅館で、隣の部屋でどんちゃん騒ぎが始まって、それがもううるさくてたまらなかったみたいな記述があるんですよね。
外国人が日本に来て、異質な感覚を覚えたみたいなところが、旅行記的に書かれてる本は何冊かあって。
文化的な音の研究をやってる人たちは、そういうところから拾ってきて、かつてこうだったみたいな話をよくするんだけど、その当時、日本の旅館ってふすま一枚だから隣の声は聞こえるのが当たり前みたいな。


そうですよね、長屋文化。
住宅事情もそうだよね。
僕は地域コミュニティの成熟にすごく興味があって、自分なりにこうじゃないかなと思ったりしているのが、家と道路の境界は曖昧な方がいいなと思ってるんですよね。


家と道路の境界が?
庭があって、庭の草が少し道路にはみ出したりっていう物理的な境界の曖昧さっていうのもあるし、光だとか音の漏れ具合みたいなものが街路に滲み出てるみたいな。
「今日も、お隣のお母さんと娘が喧嘩してるわ」みたいな。
最近は仲良くなったなとかさ、そういう声が漏れ聞こえてくる。そういう親近感。
まあ、それが騒音として受け取られるかは、ベースに人間関係があるとは思うんだけども。
昔は、多少そういうプライベートが街路に出ていくっていうのは当たり前だったんですよね。
長屋の時代も含めて。
で、だんだん高度成長時代に、騒音制御っていう観点から“遮音性能一級”のように遮断するっていうことが技術の見せ場だったわけです。遮音性能はいい方がいいに決まってるっていうか。
でも、「本当にそうか?」って。
誰もその時代は思わなかったんだけども、遮音性能は多少緩い方がいいケースだってあるわけですよね。「外界との境界に壁を立ててきっちり遮断しきって、プライベート守る」みたいな状況が、逆にそれを犯された時に過敏な反応してしまうというサイクルに陥ってんじゃないかなという気がするな。


あぁ確かに、自分の田舎はそんな感じです。
カーテンもしない時はしないですし。
でも都会は、どうしてそうなんだろう?人の目が気になっちゃうのかな。
まあそれが普通だよね。


「なにか言われちゃうかな」って、心のどっかで思っちゃうのかな。
それってやっぱり「お互いを知っているか」とか、そういう他者との関係性が、心情に影響しちゃうのかもしれないですね。
そうだね。
僕が好きなNHKの街歩きの番組で、イタリアとかの小さな街角で、おじいちゃんたちが街路のベンチに座ってビール飲みながら、町ゆく女の人たちと話している、みたいな。
そういうのっていいなって思うね。


プライベートとパブリックな空間が溶け合ってるというか、グラデーションになってる。
そこね、憧れるんです。
工業化から情報化、これから先、情報もAIが操るようになるこの時代の転換点に、そろそろ内省的に語っていいんじゃないかなって気がするんだよね。
我々が高度成長の時に技術を極め、それが社会に実装されてきた結果、どういう社会構造・文化を育む土壌を、加担して作ってきたのか。


なるほど。
時代の趨勢(すうせい)として、それが当たり前、正しい方向だと信じて、やってきたことっていうのが、結果として何を生んでるのかっていう。
いいところもたくさん生んでるんだろうけど、それだけじゃないような気がしてる。

次回はついに最終回!子どもの声や学校の音が騒音とされる背景を捉えながら、騒音の課題や地域のつながりについてトークします。お楽しみに。
【第6回】「身の周りに、技術で工夫できることはまだある」はこちら>>
プロフィール

株式会社 Sound One
音・振動分野の電子計測機器や試験機の開発を行う株式会社小野測器のグループ会社。
音を聴いた印象を評価するWebアンケートサービス「Sound One」の開発、運営を行っています。
Sound One 公式サイト
https://soundone.jp/
【異音の問題をスピーディに解決】音のWebアプリケーション
https://sound-one.net/lp/abnormal-noise/